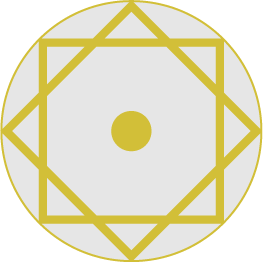先月、3月1日・2日の2日間にわたり、山梨県北杜市の身曾岐神社・瑞松宮(ずいしょうぐう)において、第4回慈敬学院中級編Ⅰを開催させていただきました。
全国から集まった40名の受講生が、2日間の行程を共にする中、祈り、学び、そしてこれからの信仰者としての歩みを見定める、まことにすばらしい機会となりましたことをご報告申し上げます。
この中級編では、特に日本の信仰の歴史と、そこからいわば必然的に生まれた私たちの会の道行きについて学びを進めていきます。この慈敬学院は、入門、初級と基礎、基本を固めた後、この中級に至ることで、ようやく会員としての学びが一つの結びとなるのだと、あらためて身にしみる機会ともなりました。
幸いなことに、受講を希望される会員も多く、急遽9月に第5回を開催させていただく運びとなりましたので、是非また多くの方たちと共に、この貴重な祈りと学びの機会を創り上げていくことを願っております。
さて、実はこの中級編の直前、私は名古屋、そして北海道へと出講しておりましたが、そこで私自身、「やはり体験に優る学びはない」と実感した出来事がありましたので、皆さまにお伝えさせていただく次第です。
まず2月23日に行なわれた名古屋合同会合で体験発表をされた方の内容がすばらしく、また教学的にも深い気づきをいただいたものとなりました。
その方は入会して6年ほどですが、とても熱心に学びを進めている女性の方で、70代の今から福祉関係の会社を興そうというほど、現実的にもパワフルな生き方をされています。
そんな彼女ですが、入会された当時、その頃のことを私も鮮明に覚えています。親族に多額の金銭をだまし取られ、まさに無一文となった。そのことをご相談にみえたのですが、私は彼女の命式を見させていただき、これは金銭カルマの解消だと確信しました。
というのも、深い金銭因縁、カルマを背負っている人というのは、必ずご先祖か、あるいは自分自身の前世においてかなりのお金を手にしている。それも多くの場合、あまり正当的ではない手段で獲得したことにより、人から恨みや妬みを買っている場合が多い。そのようなカルマを解消する手立ての一つが、いま持っている金銭を手放すこと。文字通り無くしてしまうことです。
ですから、私は彼女に「良かったですね」とお伝えしました。もろちん、これは彼女の命式、あるいは目の前にいらっしゃる彼女の霊的なところを見定めた上でお伝えした言葉ではあったのですが、案の定、彼女は最初、怒りを覚え、だからこそ「そこまで言われるのであれば、この教えをやろう」と固く決意されたそうです。
そして、そこから彼女はみ教えを真剣に学び、祈り、前回の中級編に参加するまで進んでいったのですが、やはりだまされたことへの恨み、怒りは消えない。まさに敵味方の生霊想念の塊(かたまり)です。
一方、私どもの教えの根幹は「祈り・受容・超作」、そのことを「受容」しなければいけない。
どんなことも必然として起った出来事なのだから、受容し、自分の中で消化し、昇華しなければ、決して解消することはない。それは頭では分かっているのだけれど、感情としては、だました人への恨み、憎しみが消え去ることはない――
そのような中を悶々(もんもん)としながら日々を送っていたそうですが、これは昨年11月3日、新道場の落慶の日のことだったそうです。
あの日、当然彼女も新本部道場に参列し、真新しいご神前に座ることができた。特にこの度、開眼された大日如来様の前に座った途端、涙が止まらなくなったそうです。あの大日如来様の、優しくも気高いお姿と、何よりその仏様の気が自身の胸の中に迫ってくるようで、心底から自身がゆさぶられるような体験をされたそうです。
そして、その月の不動尊例祭の時のこと。この不動尊例祭では、護摩法要厳修の前、真言宗の修法である阿字観(あじかん)瞑想について、私が独自の観点で編纂したものを参加された皆さまに行(ぎょう)じていただいておりますが、彼女もその日、映像配信にて参座されていました。
そして阿字観の行中、私のガイドで許しの瞑想――これまで出会った人の中で、どうしても許せない人を思い浮かべ、「そんなあなたを許します」という言葉で昇華させていく行法ですが、その瞬間、彼女の中には「許し」が起きたそうです。
それまで、頭では分かっていても、感情ではどうしようもなかった恨み、憎しみが、あの阿字観瞑想における許しの瞑想を行じていく中で、これは理屈なく、文字通り魂のレベルにおいて、相手の方に対する「許し」の想いが湧き上がってきたそうです。
もちろん、そこに至る様々な祈り、学び、さらには新本部道場での大日如来様との深いお出会いも力付けになったことでしょう。そして、たとえ映像を介してであれ、瞑想によって初めて、この金銭にまつわる生霊想念のカルマが解消したのです。
その出来事を涙ながらに話す彼女の体験を聞いて、私自身、学びました。「祈り・受容・超作」と言っているけれども、特に敵味方の生霊想念というのは、「受容」をさらに超えた「許し」が必要なのだと。
受容は、もちろん大切なことではあるけれど、まだ感情や思考のレベル。それが文字通り魂レベルで起きたとき、それは「許し」であって、そこまで至らなければ、やはり生霊想念怨念の解消はない。
今、世界中で起きている様々な争い。文字通り生霊想念怨念の御霊が浮かばれず、現実に見せているものではあるけれど、そのことを本気になって祈る。人々の中にある敵味方の想念を、魂レベルで「許し」にまで至ることのできる祈りがなければ、本当には解決の道には至らないのだと。
そのような意味で、私どもが日々行なっている祈り。特に理趣三昧供養において会員一人一人がさせていただいている公(おおやけ)のご供養。戦争、天災、あらゆる敵味方の想念を各家庭において祈ることのできる意味、意義、その尊さを、果たして私も含め、どれだけの人が理解し、実践していたか――そのようなことが、私の中に気づきとして、彼女の話を伺いながら痛切に感得されたのです。
そして、これは本誌面においては詳細にお伝えできないところがありますが、彼女の中に「許し」が起きた途端、現実的にも様々な証(しょう)があらわれ、先の金銭にまつわる問題が一気に解決へと向かう賜(たまわ)り物(もの)を頂戴することとなったのです。
これも、「正しい祈りは、必ず現実において結果をもたらす」という、そのことを明らかに見せていただいた出来事として、私も含めその場にいた名古屋会員一同が、あらためて深く胸に刻み込む学びを頂戴する機会となりました。
そしてもう一つ、すばらしい体験がありました。その名古屋の翌日、私は北海道・恵庭(えにわ)にある北海道道場の道東道南合同会合へと出講させていただき、さらにその次の日、永田道南会場主、清水副会場主と共に北海道檜山郡江差町(ひやまぐんえさしちょう)へと向かいました。
ここには、かむながらのみち立教当初から会員として学ばれている坂上美智子さんの住まい、職場があります。坂上さんがこの度、長年務められた看護学校を定年退職し、札幌へと戻られるということで、最後の祓いと供養をするようご神示がありましたので、今回出向いたという次第です。
といっても、車で片道5時間、往復で10時間の道程です。幸いにも天候に恵まれ、道路に支障はなかったものの、降雪などの際は、さらに時間がかかることでしょう。私が今回、心の底から感動したのは、坂上さんは、この遠い場所から毎月、欠かさず恵庭の北海道道場で開催される会合へと足を運ばれていたことです。
しかも、この江差で10年、さらに釧路(くしろ)に2年、紋別(もんべつ)で4年――いずれも片道4~5時間の距離です。そしてまた江差に戻り10年と、計26年間、必ず会場へと毎月、足を運ばれてきたのです。もちろん、大雪で交通機関がままならなかったり、ご自身の骨折など、例外はあります。が、「会合には絶対に参加する」とご自身で決められ、それを誇ることなく、当たり前のこととして実践してきた彼女の強い思いと行動力に、私は頭が下がったと同時に、これこそ真の意味での「行(ぎょう)」だと思いました。
行というと、私たちはつい何か形式的なもの、特別な修法や、祝詞を何回、お経を何遍などと捉えがちです。それも大切なのですが、その根底には、自身の中にある決意、「このことをするんだ」と自身と神仏に固く約束し、それをやり続けること。それこそが「行」の本質なのだと、あらためて私自身、深く学ばせていただきました。
仏教の世界では、「発心(ほっしん)・修行・菩提(ぼだい)・涅槃(ねはん)」という道行きがあります。「発心」がなければ、「修行」は成り立たないのです。逆に言えば、「発心」さえあれば、行の形は極端なことを言えば、何でも構わないのです。
日々の皿洗いも「行」になります。人に優しい言葉をかける、ということもそうでしょう。行の根本は、自身で発心し、そしてその行ないをやり続けることです。
ですから、坂上さんが毎月、会合に参加すると決められ、それをここまで完遂されたということ。これこそ「行」であり、坂上さんは真の意味で在家の行者(ぎょうじゃ)なのだと思いました。
坂上さんは看護学校の先生として、長年多くの優秀な看護師たちを育ててこられました。その間、様々な課題があったことは事実です。その都度、彼女はご指導を受け、真剣に祈り、そして会合へと欠かさず足を運ぶ中で、一つ一つ乗り越えてこられました。そして定年を迎え、この地でできる最後の祓いと供養を共にさせていただき、感無量の思いが私の胸にもひしひしと伝わってきました。
これから坂上さんは、さらに多くの方を導かれ、そして多くの方の希望の光となることでしょう。そのような人格形成の背後には、必ずや行――自分で決めたことを行ない続ける決意と行動力、それは表面的には目立たないかもしれないけれど、これまで確かに積み重ねてきたものの強さが、彼女の信仰を支えているのだと、深い感動と共に受け止めさせていただきました。
世の中の多くの人は、何かを手がけようとすると、必ずできない理由を探します。しかし、彼女の人生に言い訳はありません。決めて、行動する。そのシンプルなあり方こそ、結果を手にする生き方であり、その信仰行(しんこうぎょう)を満行(まんぎょう)し、この度、札幌へと戻ってくる彼女の前途が、さらに発展していくことを願う次第です。
そして私にとっても、この4月、5月は行の月となります。4月は聖地巡拝として伊勢、奈良の橿原神宮、そして本山醍醐寺へと足を運び、翌5月には熊野、高野山へと出向き、そして本会の例大祭を迎えます。これは私自身、決して欠かさないと発心し、毎年実践していることです。
皆さまご存じの通り、「紀伊山地の霊場と参詣道」は、伊勢、熊野、そして高野山を結ぶ道が世界遺産として登録され、昨年で20周年を迎えました。道が世界遺産として登録されているのは世界でたった二つですが、もう一つのフランス・スペインの「サイティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼道」はキリスト教の聖地を結ぶ道。それに比してこの熊野古道は、神道、仏教、そして修験道といった異なる信仰を結ぶ、文字通り和合の道です。
私ども、かむながらのみちの「神仏和合」の象徴として、私は様々な場面で、この熊野古道のことをお伝えしておりますが、そういった意味でも、この4月、5月の巡拝は私自身の信仰の根幹を為す行として欠かせないものと発心し、今に至っております。
今年も多くの方と巡拝を共にしますが、是非これからもさらに多くの方々と共に、この礼節の道を踏む行を共にしていきたいと願っております。信仰は学ぶだけでなく、行動することに意味があります。
すべては「知る」というところから始まり、次に「分かる」という段階。これは学んだことが自身の人生とリンクする段階です。そして次は「なる」。なるためには、行動が必要です。これが人生の絶対的な法則です。行動が要(かなめ)です。
年頭から再三、申し上げておりますように、本年は行動の年です。幸いにも、先月より皆さまに金剛神の御札をお分けすることが叶っております。この金剛神は、道祖の魂を神として祀り、私ども信仰者の人格完成、霊格向上をもたらす「実践」を後押ししてくださる、まさに行動の神です。
どうか、お互い様に、私どもに課せられた大いなる使命を自覚し、そして共に歩み、行ない続けることをあらためて神仏に誓い、そして多くの方々と共に五月の例大祭をお迎えしましょう。
今年の例大祭は、新本部道場での齋行(さいこう)となります。足運び、実践、そしてお導きです。神仏と共に歩む誇りと歓びを胸に、日々精進して参りましょう。
合掌禮拝